国試に受かった人達はあと数日で研修医生活が始まる。
以前読んだ医療小説が面白くて、これから研修医になる人に役立ちそうな内容だったので紹介する。
作者の里見清一先生は、名作ドラマ「白い巨塔」の監修をされた方。
「見送ル」は里見先生の自伝的小説である。
「見送ル」の感想
冒頭は担当の肺癌患者が亡くなる直前のシーンから始まる。
「ご本人が辛く苦しいことがないように、というのが治療の目標になります。」
「分かりました。苦しまないようにしてください。」
オーケー。この台詞を引き出せればさしあたりはほっとする。少なくとも今の私には、家族に「いい医者だ」と思わせる技術はあるだろう。
現場ではよくある光景である。
終末期では「家族に良い医者だと思わせる技術」が最も必要とされる。
結構露骨な表現が多いので、一般の人は不快感に思うかもしれないが、医療従事者としては非常に腑に落ちる内容だ。
里見先生は呼吸器内科の肺癌専門医で、色々な治療のエピソードが綴られている。
読んでいて自分の研修医時代のことを思い出した。
研修医のときの思い出
研修医生活が始まった十数年前の4月。意気揚々と向かったのは呼吸器内科の病棟だった。
入院患者はほとんどが肺癌。
肺癌は早期の場合は手術となるため呼吸器外科が治療する。一方手術適応のない進行期の患者は呼吸器内科で抗癌剤治療を行う。
つまり呼吸器内科が診るのは主に進行した肺癌ということになる。
当時は今のような分子標的薬もあまりなかったため、進行した肺癌に抗癌剤が著効するケースは稀だった。
さらに制吐剤の「5-HT3受容体拮抗薬」、「NK1受容体拮抗薬」はまだなく、プリンペランのみ。
ひどい副作用と戦いながら行った抗癌剤治療も効果が乏しい場合が多く、やるせない気分になった。
自分がそれまでイメージしていた医療と、実際の現場はかなり異なっていた。
医者の仕事は「病気を治すこと」だと思って勉強してきたが、そんなものは甘っちょろい幻想にすぎない。
治らない患者のほうが大多数なのである。
リアルな臨床現場
この本には「難しい治療がうまくいき劇的に治った」というような達成感のある話はない。
考え抜いた治療が裏目にでたり、逆に患者に流されて行った治療がうまくいったりというエピソードで、臨床の現場のリアルが綴られている。
また治療が効いたとしても、常に悪くなることを意識しておかなければならないというジレンマを抱えながら診療が行われている。
治療効果は一時的なものにすぎず、必ず再発するからである。
変に治ったつもりになってしまうとまた悪くなったときに余計きつい。
必ずまた悪くなるのは見えてるんだから。
里見先生は、治療よりも「亡くなる患者の家族をいかにして納得させて、満足して最期を迎えられるようにするか」ということに心を砕いていて、これが医療現場の現実だと思う。
医療は「患者さんを治して感謝される」みたいな勧善懲悪なシンプルな仕事ではないのである。
学生時代にこの本を読んでいたら、理想と現実のギャップに苦しむこともなかったような気がする。
もし医療にヒロイックな幻想を抱いている人がいれば、この本を読んでおくことをオススメする。
今後高齢化に伴って治せない患者はますます増えていく。
それに伴い医療の目的は「治す」から「死なせる」ことに変わっていくという。
つづく





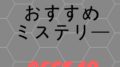

コメント